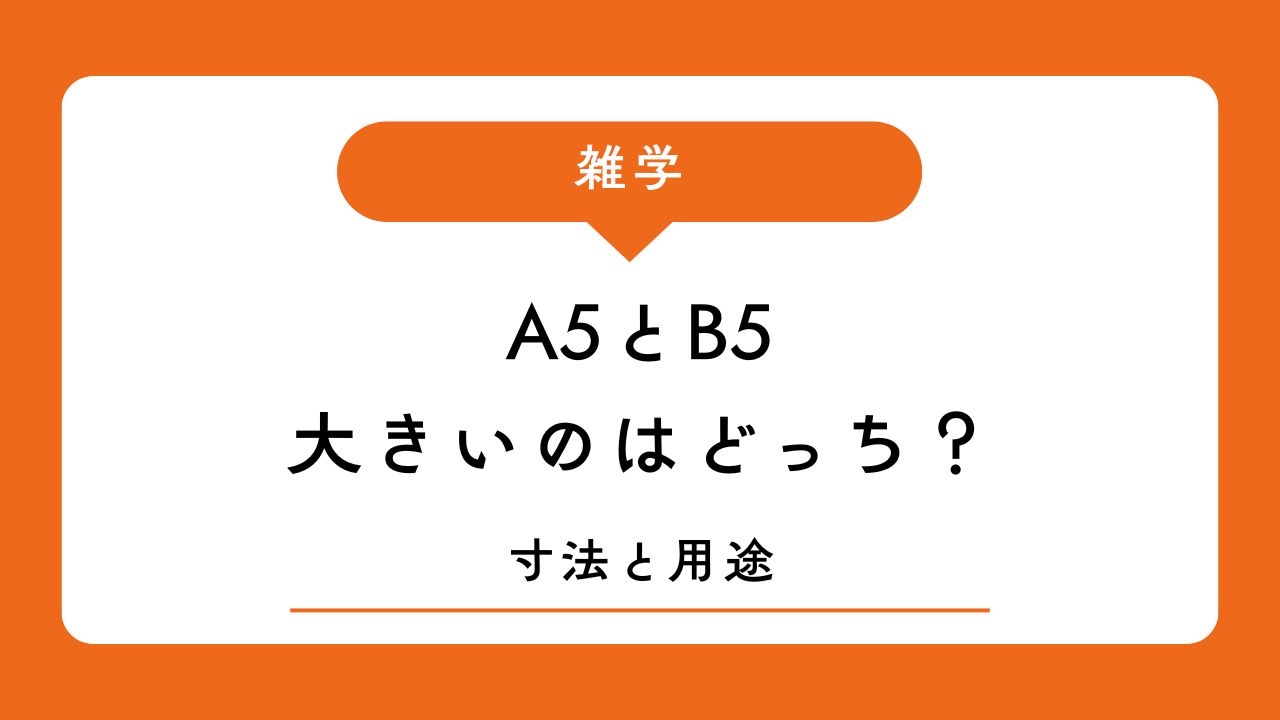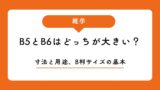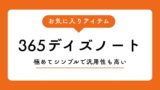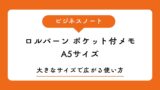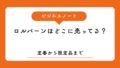ノートや手帳を選ぶ際、「A5とB5、どっちが大きかったっけ?」と思うことはありませんか。この2つのサイズは見た目が似ていますが、実は大きさも使い勝手も大きく異なります。ノートや手帳として日常的に使われるサイズでもあるので、その違いを正確に知っておくと役に立ちます。
本記事では、A5とB5のどちらが大きいのかという疑問に明確にしたうえで、それぞれの寸法や規格の基礎知識、そしてシーンに合わせた使い分けのヒントなどご紹介します。
A5とB5のサイズを比較:大きいのはB5
まず結論からお伝えすると、A5よりもB5の方が大きいサイズです。
B5はA5よりも縦横ともに大きく、面積で比較するとB5はA5の約1.5倍の広さを持っています。
それぞれの正確な寸法(ミリ表記)は次の通りです。
| サイズ | 寸法(縦×横) | 面積の目安(A5比) |
|---|---|---|
| B5 | 182mm × 257mm | 約1.5倍 |
| A5 | 148mm × 210mm | 1倍 |
B5はA5よりも書くスペースが広いため、長文を記録したり、図解を書き込んだりする用途に向いています。
また、普段よく使うA4サイズ(210mm × 297mm)と比較すると、A5サイズはA4のちょうど半分の大きさです。一方、B5サイズはA4サイズよりも一回り小さいサイズとされています。
なぜB5はA5より大きいのか?規格の違いを解説
B5とA5という表記のアルファベット(A判とB判)は、紙の規格を示しています。同じ「5」という数字がついていながらB5の方が大きいのは、規格が異なることに由来します。
A判は国際規格、B判は日本独自の規格
用紙の規格には「A判」と「B判」の2種類があり、このサイズは日本工業規格(JIS)によって定められています。
- A判: ドイツで考案された国際規格(ISO規格)で、世界中で広く使われています。A0サイズ(面積1平方メートル)を基準に、半分に折るごとに数字が大きくなります。
- B判: 日本独自の規格(JIS規格)です。江戸時代に障子などに使われていた美濃紙(みのがみ)のサイズを元に定められた、日本の伝統的な寸法に基づいているとされています。主に日本、中国、台湾といった一部の地域で使われているサイズです。
A判もB判も、紙を半分に折っても縦横の比率が変わらないという特徴(1:√2の白銀比)を持っています。
基準寸法の違い
同じ数字の組み合わせでも、B判はA判よりも基準寸法が大きく設計されています。そのため、A5とB5を比べた場合、A5よりもB5の方が約1.5倍広く、一回り大きいサイズとなるのです。
日本では、教科書や交通広告など、特定の用途でB判が使われ続けています。これは、A4とA5の中間サイズ(A5の約1.5倍)があることで便利だと感じられたり、日本人の体格やランドセルなどの持ち運びに合っているという側面があるから、という意見もあります。
A5とB5それぞれの特徴と主な用途
A5とB5は、その大きさの違いから、それぞれ得意とするシーンが異なります。用途に合わせて使い分けることが、効率的な情報整理の鍵となるでしょう。
B5サイズの特徴と用途
B5サイズは、机上で安定して使いたい、情報量を多く書き込みたい場合に適しています。
| B5の主な特徴 | B5の主な用途 |
|---|---|
| 筆記スペースが広いため、長文や図解、プリントの貼付に適している。 | 大学ノート、教科書(学習用ノートとしてポピュラー)。 |
| 安定感があり、机に置いて両手でじっくり書くのに適している。 | 雑誌、漫画週刊誌、パンフレット。 |
| サイズが大きい分、資料やプリントと並べて整理しやすい。 | レポート用紙、日記や旅行記(見開きで広く使える)。 |
B5は、昔から役所で使われていた公文書のサイズが多かったことから、学校の教科書やノートのサイズとして定着した経緯があるようです。
A5サイズの特徴と用途
A5サイズは、携帯性を重視したい、移動中など場所を選ばずメモを取りたい場合に適しています。
| A5の主な特徴 | A5の主な用途 |
|---|---|
| コンパクトで軽量なため、持ち運びやすい。 | 手帳、ビジネスノート(持ち運びに便利なサイズ)。 |
| 片手で支えやすく、立ったままでもメモが取りやすい。 | 書籍、雑誌(文庫本より一回り大きいサイズ)。 |
| バッグに入りやすく、書類や他の荷物と干渉しにくい。 | アイデアメモ、スケッチ(思いついたことを素早く残す)。 |
A5サイズは、そのコンパクトさからビジネスシーンで愛用する人も多く、小さめのバッグにも入れやすいというメリットがあります。
効率を高めるA5とB5の賢い使い分け方
A5とB5は、どちらか一方を選ぶのではなく、両方のサイズを併用することで、情報整理の効率を格段に高めることができるとされています。サイズごとの強みを活かして、目的別に使い分けるのがおすすめです。
シーン別の使い分け例
| シーン | B5の活用(詳細・一元管理) | A5の活用(携帯・要点まとめ) |
|---|---|---|
| ビジネス | 会議の議事録、情報量が多い商談、図解など。 | 移動中や外回りでの即時メモ、アイデアメモ。 |
| 学習 | 講義ノート、板書や配布プリントの貼り付け(全情報の一元化)。 | 要点まとめ、暗記カード、自習用ノート。 |
| 趣味・記録 | 日記、旅行記(文章・写真などをレイアウトしやすい)。 | 外出先でのアイデアメモやスケッチ。 |
手帳術やライフログの愛好家の間では、「家ではB5、外ではA5」といったように、場所や用途でサイズを使い分けるスタイルが定着しつつあるという傾向が見られます。
併用するメリットと工夫
情報の階層化と整理の効率化
A5とB5を併用することで、情報整理の効率化をサポートできる可能性があります。例えば、A5には要点や概要を、B5にはその詳細や補足を記録するというように、役割を分担できます。こうすることで、見返す際に情報の階層構造が明確になり、目的の情報が探しやすくなるという声があります。
周囲にスマートな印象を与える
TPO(時と場所、場合)に応じてノートのサイズを使い分けることは、周囲に合理的かつ洗練された印象を与えることにつながる可能性があります。例えば、会議ではB5のしっかりしたノート、移動中はコンパクトなA5を使う姿は、計画的に行動している印象を持たれやすいでしょう。
持ち運びの工夫
A5とB5を同時に持ち運ぶ場合は、収納方法を工夫することで荷物がかさばるのを防げます。
- 収納ケースの活用: A4収納ケースはB5ノートとA4資料が揃いやすく、A5は余裕を持って収納できます。
- バッグのポケット利用: 使用頻度の高いA5を手前ポケットに、B5を背面ポケットに分けて収納すると、移動中のメモなどもスムーズになるでしょう。
A5とB5を同時に持つ場合でも、軽量タイプやソフトカバーのノートを選ぶことで、荷物の重量を最小限に抑えることも可能です。
まとめ
「B5とA5はどちらが大きい?」という疑問について、答えはB5の方が大きいです。
A判は国際規格、B判は日本独自の規格であり、B5(182mm × 257mm)はA5(148mm × 210mm)の約1.5倍の面積を持っています。
このサイズの違いが、それぞれの用途を決定づけています。
- B5: 広い筆記面と安定感があり、講義ノートや長文、詳細な記録など机上でのじっくりとした作業に向いています。
- A5: 携帯性に優れ、片手で持ちやすいため、移動中のメモや要点の整理に適しています。
どちらのサイズも一長一短がありますが、仕事や学習、趣味の内容に応じてA5とB5を上手に使い分けることで、日常の情報整理はより快適でスムーズなものになるでしょう。ぜひ、ご自身のライフスタイルに合ったノートのサイズを試してみてください。