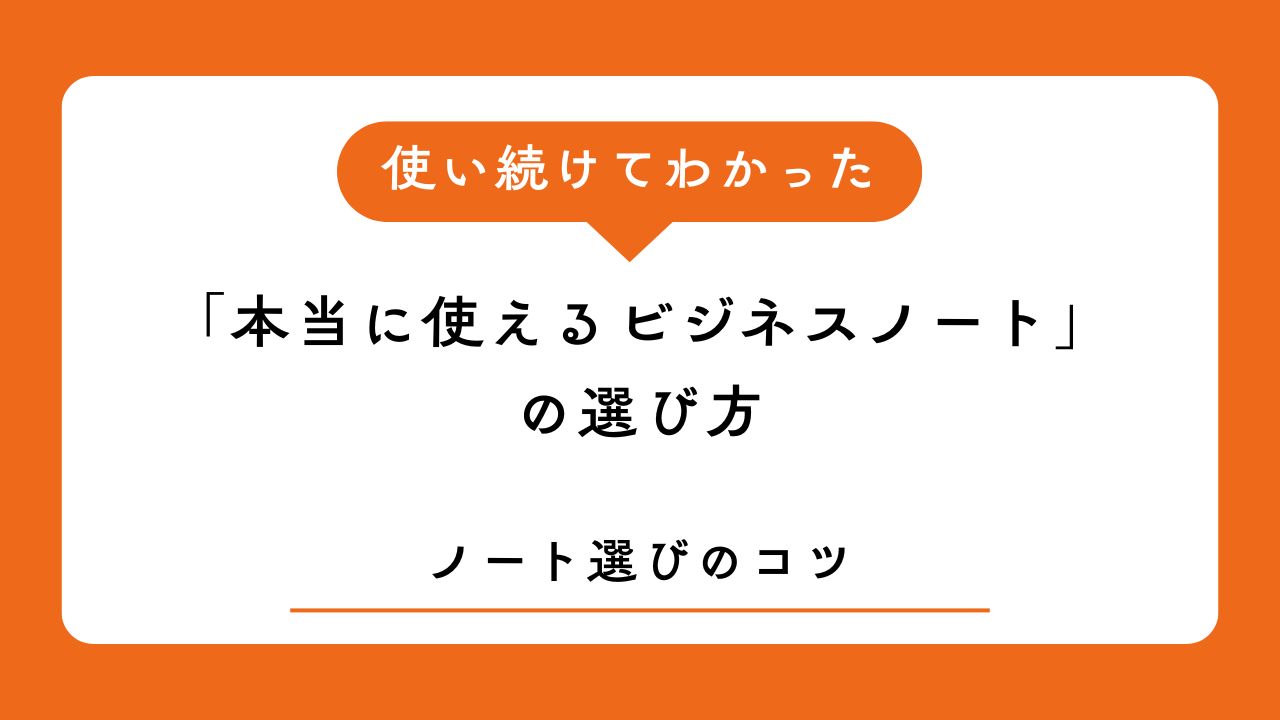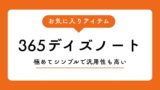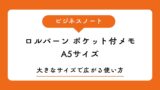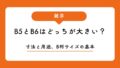デジタル全盛の時代に、なぜ紙のノートなのか。そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。私自身、365デイズノートのB5サイズを5年以上使い続けている身として、実際に様々なノートを試してきた経験から、仕事で本当に役立つノートについて考えをまとめてみました。
なぜ今も紙のノートを使うのか:実感した3つの価値
スマートフォンやタブレットでのメモが当たり前になった今でも、私が紙のノートを手放せない理由があります。
書くことで記憶に残る感覚
手書きでノートに書き込むと、デジタルメモよりも記憶に残りやすいと感じています。5年以上使い続けてきて実感するのは、書く行為そのものが思考を整理する時間になっているということです。ミーティングでデジタル端末を使う同僚もいますが、私の場合、手書きの方が後から「あの時こう考えていた」という記憶が蘇りやすい。筆跡や図の配置まで記憶の手がかりになるんです。
情報を一か所にまとめる安心感
私が365デイズノートを選んだ理由の一つが、「このノートさえ見れば良い」という気楽さによって、雑然としかけた脳内のストレスが低減する点でした。仕事では様々な情報が飛び交いますが、重要なことを一冊のノートに集約することで、情報を探す手間が大幅に減ります。図やレイアウトも自由に描けるため、文字だけでは伝わらない情報も直感的に記録できるのです。
思考を深める道具として
ノートに書くという行為は、頭の中の情報を整理してアウトプットする訓練になります。長年続けてきて感じるのは、要点をまとめる力や、自分の言葉で表現する力が自然と磨かれていくということ。結果的に、レポートの作成やプレゼンなども以前よりスムーズになりました。
サイズ選びの実際:B5を選んだ理由
ノート選びで最初に悩むのがサイズです。私は最終的にB5サイズに落ち着きましたが、それまでには試行錯誤がありました。
携帯性と書き込みスペースのバランス
A5サイズは確かに持ち運びやすく、ビジネスバッグにもすんなり収まります。外回りが多い方や、複数の場所を移動する方には最適でしょう。実際、A5サイズはビジネスパーソンに人気で、見開きで使えば広々と書き込めるのが魅力です。
一方、私が選んだB5サイズは、デスクワークが多い私の働き方に合っていました。365デイズノートのB5サイズは24時間軸があり、方眼紙で自由に書けるため、理想の日記帳・業務記録ノートになると感じています。見開きにすると、一日の流れと詳細なメモを同時に俯瞰できる広さが確保できます。
A4サイズも検討しましたが、持ち運びを全く考えないわけではないため、サイズと機能性のバランスでB5に決めました。
罫線は方眼を選んで正解だった
横罫か方眼かで迷った時期もありましたが、現在は方眼に落ち着いています。
横罫(A罫・B罫)の良さと限界
横罫は文章の行間を揃えやすく、長文を書く際やミーティングなどの内容をまとめる際に重宝するのは確かです。罫幅7mmのA罫はゆったり書きやすく、6mmのB罫は細かく記入したい方に向いています。
ただ、文章だけでなく図表や矢印、フローチャートなども頻繁に書く場合、横罫の制約が気になってきます。
方眼罫の自由度
365デイズノートの方眼紙は、文字をきれいに揃えられるだけでなく、図や表の作成にも役立つのも魅力のひとつです。
縦線も横線も引きやすく、表組みも簡単。文章を書くときは横罫のように使い、図を描くときは自由に使える。この柔軟性が、様々な業務に対応できる理由です。
紙表面の適度なザラツキによって筆記しやすく、付箋紙の定着も容易なのも、日々の使用で実感しているポイントです。
綴じノートという選択
私は綴じノート派ですが、これも働き方によります。
綴じノートのメリット
365デイズノートは布クロスの表紙や360°開く糸かがり製本を採用した丈夫な設計で、368ページあるとは思えない薄さが特徴です。5年間で何冊も使ってきましたが、保管しても場所を取らず、過去のノートを参照するときも便利です。
見開きでフラットに開くため、ページの端まで広々と書き込めるのも大きなメリット。長期保存が前提の業務記録には、やはり綴じノートが適していると感じます。
リングノートの進化
ただし、コクヨのソフトリングノートなど、独自開発の柔らかいリングを採用したものは、書くときにリングが手に当たって邪魔になるというデメリットを解消しているそうです。立ったままメモを取る機会が多い方や、ページを折り返して使いたい方には、こうした進化したリングノートも選択肢になるでしょう。
実践している効率的な使い方
ここでは私のノートの使い方をご紹介します。
すべてを書かない勇気
会議やセミナーなどで、話されている内容をすべてメモしようとすると、かえって大切なポイントを聞き逃してしまいます。私が意識しているのは、会議の場合は、目的やテーマ、決定事項や保留事項、注意点、セミナーの場合は、キーメッセージや事例・データなど、核となる部分だけを確実に押さえること。不明点には「?」マークをつけて、後で確認できるようにしています。
余白を活かす情報設計
意識的に余白を作ることで、ノートがすっきりして読みやすくなるだけでなく、情報の追加やひらめきを書き足すスペースが確保できます。私の場合、ノートの右側3分の1程度をメモ欄として空けておき、後日気づいたことや関連情報を追記できるようにしています。
色は3色まで、ルールを決める
色ペンは便利ですが、使いすぎると逆効果です。調べてみると以下のようなルールを決めてる人が多いようです。
- 黒:基本的な記録
- 赤:重要事項、期限、確認必要箇所
- 青:後日追記した情報や気づき
このようなシンプルなルールを設けておくと、過去のノートを見返したときも情報が見つかりやすくなります。
記号と略語の活用
「重要:★」「疑問:?」「増加:↑」といった記号を活用することで、効率的に情報を記録できるのは確かです。私も自分なりの記号体系を作って使っています。
ただし、あまり複雑にしすぎると後で見返したときに分からなくなるので、シンプルで直感的な記号に絞ることをおすすめします。
365デイズノートを選んだ理由
シンプルな設計思想
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートで、使いやすさを追求して設計した、編集者も納得のEditor’s Seriesというコンセプトに共感しました。
曜日と日付設定が自由にできるので、1月始まりでなくても年中使い始められるのも、仕事のノートとして使いやすいポイントです。
薄くて軽い、でも丈夫
薄い紙を採用しているため、全部で368ページあるとは思えない薄さで、かさばらず持ち運べるのに、実際に使ってみると意外と丈夫です。本文紙は様々なタイプの筆記具と相性が良く、文字が裏抜けしにくいのも日々実感しています。
ただし、紙が薄いため筆圧が高いと裏写りすることがあり、フリクションボールは避けるべきという注意点はあります。私はジェルインクのボールペンを使っていますが、問題なく使えています。
高価だが、投資する価値がある
正直なところ、高価なことは難点です。とはいえ、仕事の生産性を高めるためには必要な投資だとも思っています。もちろん仕事のスタイルは人それぞれなので、万人にあうノートとは思いませんが、私自身は365デイズノートを使うようになって、より生産的なアイデアも生まれるようになったと実感しています。
他の人気ノートについて調べてみた
365デイズノート以外にも、ビジネスシーンで評価の高いノートがあります。参考までにご紹介します。
デザインと機能性重視なら
デルフォニックスのロルバーン ポケット付メモA5は、シンプルで飽きのこないデザインに加えて、全ページにミシン目が付いており、メモをスマートに渡せる点が支持されているそうです。巻末のクリアポケットも便利とのこと。
書き心地にこだわるなら
日本ノートのPremium C.D. NOTEBOOKなどに使われるオリジナルの筆記用紙は、シルクのようななめらかな書き心地が特徴で、万年筆やボールペンのインクが滲みにくいとされています。また、デザインフィルのMDノートは、ペン先を受け止めてくれるふっくらとした紙質が、書く喜びを味わいたい層から評価されているようです。
私も書き心地には敏感な方ですが、365デイズノートの紙質も十分満足できるレベルだと感じています。
狭い場所での使用を考えるなら
コクヨのソフトリングノートは、独自開発の柔らかいリングを採用しており、書くときにリングが手に当たって邪魔になるという従来のリングノートのデメリットを解消できる進化型です。
また、プラスのCa.CreaはA4三つ折りサイズで、スーツの内ポケットなどにも収まりやすく、耐久性の高い紙クロスを表紙に使用しているため、水滴がこぼれても拭き取れるという実用性の高さが特徴だそうです。
おわりに
5年以上365デイズノートのB5サイズを使い続けてきて、ノートは単なる記録ツールではなく、思考を整理し、情報を資産化するための道具だと実感しています。
ただし、これは私の働き方に合っていたからこその結論です。外回りが多い方ならA5サイズの方が便利でしょうし、文章中心の業務なら横罫の方が使いやすいかもしれません。立ったままメモを取ることが多いなら、リングノートの方が適しているはずです。
大切なのは、自分の働き方や用途に合ったノートを選ぶこと。そして、選んだノートを継続して使い込むことで、自分なりの使い方が確立されていきます。
もし今使っているノートに不満を感じているなら、この記事が新しいノート選びの参考になれば幸いです。